2015年日本朱子学研究综述
| 内容出处: | 《朱子学年鉴.2015》 图书 |
| 唯一号: | 130820020230001521 |
| 颗粒名称: | 2015年日本朱子学研究综述 |
| 分类号: | B244.75 |
| 页数: | 5 |
| 页码: | 134-139 |
| 摘要: | 本文记述了2015年日本朱子学研究综述包括方法论、思想史讲座、思想史情况。 |
| 关键词: | 日本 朱子学研究 综述 |
内容
1.「方法論」への問い
今日の日本学術界では、日本朱子学は「東洋哲学」「政治思想史」「倫理思想史」等々のさまざまな専門分野から研究がなされているが、質量ともにその研究の中核をなすのは、「日本思想史」と名指されたディシプリンである。日本思想史学会は現在、個人730人、団体31機関の会員を擁しm、学会誌『日本思想史学』を逐年で発刊している。すでに47号•を重ねた『日本思想史学』は、とくに日本近世の儒教研究については、——古代・中世思想における仏教研究や国文学研究との競合状況が存在しなし、ことを大きな要因として一一日本国内ではもっとも水準の高レ、論考が掲載される雑誌であると、衆目の一致する所である。
その日本思想史学会では、本年(2015年)、思想史研究の「方法論」をめく、って丁々発止の議論が交わされた。まず2015年9月12日には、「思想史の対話」と題する研究会が東京大学本郷キャンパス(東京都文京区)で行われた。そこでは現学会長である前田勉(愛知教育大学教授)が、戦後の日本近世思想史研究一実質的にはその過半が儒教研究である一をリードした丸山真男、安丸良夫、子安宣邦らがそれぞれに描いた近世思想史の「全体像」を総括したうえで、これからの思想史の「全体像」の描き方について提言し、それに報告者(板東)がいくつかの応答を行なった。ついで、10月17日•18日両日にわたって早稲田大学戸山キャンパス(東京都新宿区)で開催された日本思想史学会大会では、第一日の午後に「思想史学の問い方一2つの日本思想史講座をふまえてーー」と題した全体シンポジウムが開催された。こちらは近世思想史/儒教研究に限定されたものではなレ、が、前田とならんで東北大学出身の日本儒教研究の重鎮である田尻祐一郎(東洋大学教授)の「戦後の近世思想史研究をふりかえる」と題する報告に対し、澤井啓一(恵泉女学園大学名誉教授)と高山大毅(駒澤大学講師)とがそれぞれ精緻に論評を加えた[2]。
なぜ今になって、日本の研究者たちはその研究対象、すなわち朱子学の移入を!1蒿矢とする日本儒教に対して、その「全体像」•「問い方」•「方法論」等々の大仰な問いを問うのか。そこには、おそらく東アジアの他の諸地域の儒教研究には見出せない、日本特有の事情が存する。それは端的にいって、他の地域とは異なり、日本には儒教を、ーー今に活かそうとするにせよ、対決せんとするにせよーー“われわれの伝統”として捉える了解が存在しない、ということである。無論、日本にも19世紀の近代化を越えて、基層的な民俗行事や行動様式の中に融けこみ、底流し続けている思想伝統は存在する。しかしそれは「仏教」や「神道」として観念される場合が大半であり、決して「儒教」ではない。そこで、“なぜ儒教を問うのか”という問いを、日本の研究者はつねに意識しながら研究を進めざるをえないのである。この単純な問いに研究者たちが明快に答えることができないならば、日本の人文学の壊滅的な状況の中で、近世に生産された無数の朱子学•新儒学をめぐるテクスト群は、いたずらに各地の書庫に死蔵されるだけとなりかねない。
その意味で、上記の二つの会合の中で、前田と田尻の両者がともに、丸山真男と子安宣邦との近世思想史研究を重点的に取り上げているのは示唆的である。名著『日本政治思想史研究』(東京大学出版会、1952)で近世における朱子学から徂探学・国学への展開過程の中に日本の内発的近代性の萌芽(と、限界と)を見出した丸山の議論は、戦後の日本と、日本思想史学との再出発に際して、多くの人びとを引き付けた。今日にまで至る日本思想史学内での近世思想の“偏重”には、丸山の影響が大きい。また、1990年代にフランスアメリ力の最新の批評理論を近世思想研究に導入した子安宣邦の研究は、非常に抽象度の高い分析概念を駆使するものでありながら、同時に近•現代日本のナショナリズムへの抜本的な批判という、極めて明瞭かつ現代的な意義をも併せ持つものであった⑶。両者はともに、実証的な文献研究の視点からは批判も受けがちであるが、強い補助線を引き、“物語”を提示することで、儒教が“伝統”としてのコンセンサスをもたなレ、日本において、日本儒教を主題的にとりあげる現代的意義を明快に示し、多くの日本人の関心を惹起したその貢献には多大なものがある。彼らの仕事が今想起されるのは、日本儒教をもう一度、多くの日本人にとって切実な意義を帯びた対象として捉えなおすことが焦眉の課題となっているためにほかならない。
このような現状認識を共有しつつも、前田と田尻との提言は対照的である。丸山を越える近世儒教の「グランドセオリー」の構築に意欲的な前田は、近世日本の基底思想は朱子学ではなく武家政権の基本教養としての「兵学」であり、朱子学は外来思想として部分的地位を占めたに過ぎないとする把握⑷や、また近世後期における儒教経典の「会読」の場が、近代以降の自由な言論空間へと直結したとする「会読」論⑶など、膨大な知識に裏付けされた斬新な「全体像」を提言し続け、現在に至るまで日本儒教研究を強力に牽引している。対して、山崎闇斎や徂铢学派の篤実な研究で知られる田尻[6]は、「偉大な思想家とじっくり対話を重ねるという態度(方法)が、今日の思想史研究で弱体化しているのではないか」(上記大会発表資料)と指摘する。田尻が提唱するその「態度」あるいは「方法」とは、『論語』なり『書経』なりを味読し、聖賢との内的対話を通じて真理の獲得、ないしは人格の修養を目指すという、むしろ儒教に伝統的な「態度」「方法」である。今日の日本の人文学はますますそのような余裕を許さない方向に向かいつつあるが、儒教が「読書」•「学文」を基底的な営為とする思想であるこ세ま、繰り返し想起されねばならないだろう。
2.二つの思想史講座
田尻・澤井・高山による学会シンポジウムの副題に「2つの日本思想史講座をふまえて」とあったように、2015年は、日本思想史学関連書籍の主要な版元である岩波書店とぺりかん社との両者からそれぞれに上梓された新たな日本思想史講座が完結した年としても、特徴づけられる。前節でとりあげた活発な思想史の「方法論」をめぐる議論は、両講座の総括としての意義も併せもっている。
岩波書店から茹部直・黒住眞•佐藤弘夫•末本文美士を編集委員として発刊された『岩波講座日本の思想』は全八巻で、テーマごとの巻分けとなっている。それぞれの巻が扱うテーマは「「日本」と日本思想」「場と器」「内と外」「自然と人為」「身と心」「秩序と規範」「儀礼と創造」「聖なるものへ」(巻数順)であり、現在関心が持たれている問題圏の布置を彷彿させる⑺。ーた、ぺりかん社から同じメンバーに田尻祐一郎を加えた五名を編集委員として発刊された『日本思想史講座』は全五巻で、「古代」「中世」「近世」「近代」の時代ごとの巻に加えて、第五巻では「方法」を論じる。こちらは時代順であるのでいっそう利便性が高く、とくに「近世」の巻(2012年刊)は日本国内での日本儒教の現在の研究状況の概要を把握するためには絶好の書となっている。
2014年に完結した岩波講座とは異なり、ぺりかん社版講座の最終巻の完成は難航し、本年12月の刊行をもって、両講座はようやく完結を迎えた。そこで、このペりかん社版講座第五巻(『日本思想史講座5——方法』、ぺりかん社、2015.12)を、本年を代表する日本思想史研究の著作と位置づけ、日本朱子学に関係する限りでの内容の簡潔な紹介を行ないたい。
内容としては大きく四部にわかれる。まずI•「研究の課題と方法」では黒住眞(東京大学教授)と片岡龍(東北大学教授)とが日本思想史の「研究と課題」を提示する。次にH.「方法の諸相」では「擬古」「論争」「訓読」「書物」「性とジェンダー」「環境」等々の具体的な研究視角を、それぞれの第一人者が概説している。さらにm.「世界のなかの日本思想史ーー海外からのアプローチ」では中国韓国欧米といった「海外からのアプローチ」が報告される。このうち卞崇道と呉光輝と藍弘岳による中国の研究状況が、日本儒教を中心的な主題とする。最後にIV•「日本思想史へー一ガイダンス」では、「神道」「仏教」「儒教」「キリ자教」等の諸思想ごとに簡便な「ガイダンス」が付されている。「儒教」の執筆者は一昨年の本稿でも取り上げた土田健次郎(早稲田大学教授)である。また、巻末に「日本思想史学関係文献一覧」と最新の「日本思想史年表」を掲載して学習者のために有益である。特に文献一覧の「近世•一般」の欄には、今日なお重要と思われる日本儒教研究文献が、ほぼ過不足なくリストアップされており、海外からの研究にも大いに資するであろう。
3.「訓読」の思想史
今日、日本儒教研究の上で盛んに論じられており、日本朱子学とも深く相関するテーマとして、ぺりかん社版講座にも取り上げられていた「訓読」が挙げられる。このテーマの国内での第一人者は、講座の当該箇所の執筆者でもある中村春作(広島大学教授)である。中村の「訓読」に関する論は、ほかにも岩波書店版講座第二巻所収の「訓読と翻訳ーー原典との間をつなぐ」があり、また文部科学省科学研究費•特定地域研究「東アジアの海域交流と日本伝統文化の形成」(2005-2009、代表:小島毅)内の、彼を首魁とする「日中儒学班」の研究成果をまとめた浩瀚な『「訓読」論—ー東アジア漢文世界と日本語』(勉誠出版、2008)、『続「訓読」論ーー東アジア漢文世界の形成』(勉誠出版、2010)にも、さまざまな専門家による専論とともに、大変明晰な総説を掲載している。以下、これらのうちで、もっとも簡にして要を得た論考と思われる岩波講座所収の「訓読と翻訳」に拠りつつ、本テーマの射程と面白さとを紹介したい⑻。
文献上では六世紀の儒教経典渡来よりこのかた、日本人は長く『書経』『論語』等の経典類を中国語として•中国語の音で読むのではなく、本文に独自の記号を付して、日本語とへと「翻訳」して読んできた。そこでは無論、中国語と日本語とで語順の違う語の順番を入れ替え、(日本語話者からすれば)中国語に存在しない助辞を補い、中国語の単語をそれに該当する日本語の語彙で読みかえる等々の作業が行われる。これが「訓読」である。まがりなりにもこの技法が今日に至るまで中等•高等国語教育の中で存続しているからこそ、古典中国語の文字列を見る現在の日本人の脳内では、中国語の音の連なりではなく、「訓読」された変格的な日本語の文語文が読み上げられるようになっているのである。「訓読」は漢文文化圏の周縁という日本の位置が成立させた、巧みな翻訳の技法である。
しかし、この千年以上続く「訓読」の伝統には一大転機が存在した。それはまさに朱子学の導入によって起こったのである。十五世紀のことである。当時、貴族社会の退廃によって、「訓読」の技法は世襲の博士の家に独占されていた。そこでは「秘伝的、職人芸的漢文読書法」(p.36)が主流となり、きわめて閉鎖的な空気が醸成されていた。しかしそこに、「儒学は晦庵に原づかざれば、以て学と為さず」(『桂庵和尚家法訓点』)と朱子学を尊信した禅僧•桂庵玄樹(1427-1508)が現われ、より一般的で公開的な訓読の技法を開発した。桂庵から南浦文之(1555-1620)へと継承され、さらに近世の林羅山•山崎闇斎•佐藤一斎といった醇儒たちによって一般化したこの新しい訓読法は、博士家の「古法」との対照で「近世訓点」と呼ばれる。十七世紀以降の日本における経典類は、大半が、この近世訓点に属する林羅山の「道春点」で訓読されたのである。
そしてこの訓読の転換は、「単なる技法の転換ではなく」(同)、「朱子学受容と連動した、一種の思想的転回であった。」(同)桂庵点、さらには近世訓点一般の特徴は、「而」「矣」などの「助字」を丁寧に読んでいく点に求められるが、「この桂庵の、「置き字」一字一字を必ず訓読し、原文の一字一字をすべて日本語に直していこうとする姿勢は、経書の一字一字をすべて論理的、抽象的に概念規定し、解釈しっくしていく朱熹の注釈の方法に相応するものであった」(p.37)と中村は結論づける。「理一分殊」を理論的前提としつつ、格物致知の実践として入念に経書を注釈してゆく朱熹の姿勢の日本における対応物が、誰にでも公開された簡明平易な近世訓点なのである。
その後も、朱子学の「理」の思想を否定した荻生徂徳が、まさに訓読の廃止を提唱したり、さらには近世末期の知識人たちの骨身に染みついていた訓読文体が開化期の書記文体の母体となり、今日の日本の書き言葉までもその決定的な影響下にあったりと、「訓読」と朱子学とをめぐる問題圏は、さながら日本儒教史•日本語史•日本文学史•日本文化史等々の最肝要の結節点をなしているといって過言ではない。今日の日本人が読み、書く言語そのものが、朱子学のはるかな残響のもとにあるのである。こうした「訓読」の重要さについては、哲学・歴史学の方面の研究者のみでなく、もちろん文学研究者も注目するところであり[9]、現在「訓読」研究界隈は、おのずと活気ある学際研究の様相を呈してレ、る。V、っそうの成果が俟たれるところである。
今日の日本学術界では、日本朱子学は「東洋哲学」「政治思想史」「倫理思想史」等々のさまざまな専門分野から研究がなされているが、質量ともにその研究の中核をなすのは、「日本思想史」と名指されたディシプリンである。日本思想史学会は現在、個人730人、団体31機関の会員を擁しm、学会誌『日本思想史学』を逐年で発刊している。すでに47号•を重ねた『日本思想史学』は、とくに日本近世の儒教研究については、——古代・中世思想における仏教研究や国文学研究との競合状況が存在しなし、ことを大きな要因として一一日本国内ではもっとも水準の高レ、論考が掲載される雑誌であると、衆目の一致する所である。
その日本思想史学会では、本年(2015年)、思想史研究の「方法論」をめく、って丁々発止の議論が交わされた。まず2015年9月12日には、「思想史の対話」と題する研究会が東京大学本郷キャンパス(東京都文京区)で行われた。そこでは現学会長である前田勉(愛知教育大学教授)が、戦後の日本近世思想史研究一実質的にはその過半が儒教研究である一をリードした丸山真男、安丸良夫、子安宣邦らがそれぞれに描いた近世思想史の「全体像」を総括したうえで、これからの思想史の「全体像」の描き方について提言し、それに報告者(板東)がいくつかの応答を行なった。ついで、10月17日•18日両日にわたって早稲田大学戸山キャンパス(東京都新宿区)で開催された日本思想史学会大会では、第一日の午後に「思想史学の問い方一2つの日本思想史講座をふまえてーー」と題した全体シンポジウムが開催された。こちらは近世思想史/儒教研究に限定されたものではなレ、が、前田とならんで東北大学出身の日本儒教研究の重鎮である田尻祐一郎(東洋大学教授)の「戦後の近世思想史研究をふりかえる」と題する報告に対し、澤井啓一(恵泉女学園大学名誉教授)と高山大毅(駒澤大学講師)とがそれぞれ精緻に論評を加えた[2]。
なぜ今になって、日本の研究者たちはその研究対象、すなわち朱子学の移入を!1蒿矢とする日本儒教に対して、その「全体像」•「問い方」•「方法論」等々の大仰な問いを問うのか。そこには、おそらく東アジアの他の諸地域の儒教研究には見出せない、日本特有の事情が存する。それは端的にいって、他の地域とは異なり、日本には儒教を、ーー今に活かそうとするにせよ、対決せんとするにせよーー“われわれの伝統”として捉える了解が存在しない、ということである。無論、日本にも19世紀の近代化を越えて、基層的な民俗行事や行動様式の中に融けこみ、底流し続けている思想伝統は存在する。しかしそれは「仏教」や「神道」として観念される場合が大半であり、決して「儒教」ではない。そこで、“なぜ儒教を問うのか”という問いを、日本の研究者はつねに意識しながら研究を進めざるをえないのである。この単純な問いに研究者たちが明快に答えることができないならば、日本の人文学の壊滅的な状況の中で、近世に生産された無数の朱子学•新儒学をめぐるテクスト群は、いたずらに各地の書庫に死蔵されるだけとなりかねない。
その意味で、上記の二つの会合の中で、前田と田尻の両者がともに、丸山真男と子安宣邦との近世思想史研究を重点的に取り上げているのは示唆的である。名著『日本政治思想史研究』(東京大学出版会、1952)で近世における朱子学から徂探学・国学への展開過程の中に日本の内発的近代性の萌芽(と、限界と)を見出した丸山の議論は、戦後の日本と、日本思想史学との再出発に際して、多くの人びとを引き付けた。今日にまで至る日本思想史学内での近世思想の“偏重”には、丸山の影響が大きい。また、1990年代にフランスアメリ力の最新の批評理論を近世思想研究に導入した子安宣邦の研究は、非常に抽象度の高い分析概念を駆使するものでありながら、同時に近•現代日本のナショナリズムへの抜本的な批判という、極めて明瞭かつ現代的な意義をも併せ持つものであった⑶。両者はともに、実証的な文献研究の視点からは批判も受けがちであるが、強い補助線を引き、“物語”を提示することで、儒教が“伝統”としてのコンセンサスをもたなレ、日本において、日本儒教を主題的にとりあげる現代的意義を明快に示し、多くの日本人の関心を惹起したその貢献には多大なものがある。彼らの仕事が今想起されるのは、日本儒教をもう一度、多くの日本人にとって切実な意義を帯びた対象として捉えなおすことが焦眉の課題となっているためにほかならない。
このような現状認識を共有しつつも、前田と田尻との提言は対照的である。丸山を越える近世儒教の「グランドセオリー」の構築に意欲的な前田は、近世日本の基底思想は朱子学ではなく武家政権の基本教養としての「兵学」であり、朱子学は外来思想として部分的地位を占めたに過ぎないとする把握⑷や、また近世後期における儒教経典の「会読」の場が、近代以降の自由な言論空間へと直結したとする「会読」論⑶など、膨大な知識に裏付けされた斬新な「全体像」を提言し続け、現在に至るまで日本儒教研究を強力に牽引している。対して、山崎闇斎や徂铢学派の篤実な研究で知られる田尻[6]は、「偉大な思想家とじっくり対話を重ねるという態度(方法)が、今日の思想史研究で弱体化しているのではないか」(上記大会発表資料)と指摘する。田尻が提唱するその「態度」あるいは「方法」とは、『論語』なり『書経』なりを味読し、聖賢との内的対話を通じて真理の獲得、ないしは人格の修養を目指すという、むしろ儒教に伝統的な「態度」「方法」である。今日の日本の人文学はますますそのような余裕を許さない方向に向かいつつあるが、儒教が「読書」•「学文」を基底的な営為とする思想であるこ세ま、繰り返し想起されねばならないだろう。
2.二つの思想史講座
田尻・澤井・高山による学会シンポジウムの副題に「2つの日本思想史講座をふまえて」とあったように、2015年は、日本思想史学関連書籍の主要な版元である岩波書店とぺりかん社との両者からそれぞれに上梓された新たな日本思想史講座が完結した年としても、特徴づけられる。前節でとりあげた活発な思想史の「方法論」をめぐる議論は、両講座の総括としての意義も併せもっている。
岩波書店から茹部直・黒住眞•佐藤弘夫•末本文美士を編集委員として発刊された『岩波講座日本の思想』は全八巻で、テーマごとの巻分けとなっている。それぞれの巻が扱うテーマは「「日本」と日本思想」「場と器」「内と外」「自然と人為」「身と心」「秩序と規範」「儀礼と創造」「聖なるものへ」(巻数順)であり、現在関心が持たれている問題圏の布置を彷彿させる⑺。ーた、ぺりかん社から同じメンバーに田尻祐一郎を加えた五名を編集委員として発刊された『日本思想史講座』は全五巻で、「古代」「中世」「近世」「近代」の時代ごとの巻に加えて、第五巻では「方法」を論じる。こちらは時代順であるのでいっそう利便性が高く、とくに「近世」の巻(2012年刊)は日本国内での日本儒教の現在の研究状況の概要を把握するためには絶好の書となっている。
2014年に完結した岩波講座とは異なり、ぺりかん社版講座の最終巻の完成は難航し、本年12月の刊行をもって、両講座はようやく完結を迎えた。そこで、このペりかん社版講座第五巻(『日本思想史講座5——方法』、ぺりかん社、2015.12)を、本年を代表する日本思想史研究の著作と位置づけ、日本朱子学に関係する限りでの内容の簡潔な紹介を行ないたい。
内容としては大きく四部にわかれる。まずI•「研究の課題と方法」では黒住眞(東京大学教授)と片岡龍(東北大学教授)とが日本思想史の「研究と課題」を提示する。次にH.「方法の諸相」では「擬古」「論争」「訓読」「書物」「性とジェンダー」「環境」等々の具体的な研究視角を、それぞれの第一人者が概説している。さらにm.「世界のなかの日本思想史ーー海外からのアプローチ」では中国韓国欧米といった「海外からのアプローチ」が報告される。このうち卞崇道と呉光輝と藍弘岳による中国の研究状況が、日本儒教を中心的な主題とする。最後にIV•「日本思想史へー一ガイダンス」では、「神道」「仏教」「儒教」「キリ자教」等の諸思想ごとに簡便な「ガイダンス」が付されている。「儒教」の執筆者は一昨年の本稿でも取り上げた土田健次郎(早稲田大学教授)である。また、巻末に「日本思想史学関係文献一覧」と最新の「日本思想史年表」を掲載して学習者のために有益である。特に文献一覧の「近世•一般」の欄には、今日なお重要と思われる日本儒教研究文献が、ほぼ過不足なくリストアップされており、海外からの研究にも大いに資するであろう。
3.「訓読」の思想史
今日、日本儒教研究の上で盛んに論じられており、日本朱子学とも深く相関するテーマとして、ぺりかん社版講座にも取り上げられていた「訓読」が挙げられる。このテーマの国内での第一人者は、講座の当該箇所の執筆者でもある中村春作(広島大学教授)である。中村の「訓読」に関する論は、ほかにも岩波書店版講座第二巻所収の「訓読と翻訳ーー原典との間をつなぐ」があり、また文部科学省科学研究費•特定地域研究「東アジアの海域交流と日本伝統文化の形成」(2005-2009、代表:小島毅)内の、彼を首魁とする「日中儒学班」の研究成果をまとめた浩瀚な『「訓読」論—ー東アジア漢文世界と日本語』(勉誠出版、2008)、『続「訓読」論ーー東アジア漢文世界の形成』(勉誠出版、2010)にも、さまざまな専門家による専論とともに、大変明晰な総説を掲載している。以下、これらのうちで、もっとも簡にして要を得た論考と思われる岩波講座所収の「訓読と翻訳」に拠りつつ、本テーマの射程と面白さとを紹介したい⑻。
文献上では六世紀の儒教経典渡来よりこのかた、日本人は長く『書経』『論語』等の経典類を中国語として•中国語の音で読むのではなく、本文に独自の記号を付して、日本語とへと「翻訳」して読んできた。そこでは無論、中国語と日本語とで語順の違う語の順番を入れ替え、(日本語話者からすれば)中国語に存在しない助辞を補い、中国語の単語をそれに該当する日本語の語彙で読みかえる等々の作業が行われる。これが「訓読」である。まがりなりにもこの技法が今日に至るまで中等•高等国語教育の中で存続しているからこそ、古典中国語の文字列を見る現在の日本人の脳内では、中国語の音の連なりではなく、「訓読」された変格的な日本語の文語文が読み上げられるようになっているのである。「訓読」は漢文文化圏の周縁という日本の位置が成立させた、巧みな翻訳の技法である。
しかし、この千年以上続く「訓読」の伝統には一大転機が存在した。それはまさに朱子学の導入によって起こったのである。十五世紀のことである。当時、貴族社会の退廃によって、「訓読」の技法は世襲の博士の家に独占されていた。そこでは「秘伝的、職人芸的漢文読書法」(p.36)が主流となり、きわめて閉鎖的な空気が醸成されていた。しかしそこに、「儒学は晦庵に原づかざれば、以て学と為さず」(『桂庵和尚家法訓点』)と朱子学を尊信した禅僧•桂庵玄樹(1427-1508)が現われ、より一般的で公開的な訓読の技法を開発した。桂庵から南浦文之(1555-1620)へと継承され、さらに近世の林羅山•山崎闇斎•佐藤一斎といった醇儒たちによって一般化したこの新しい訓読法は、博士家の「古法」との対照で「近世訓点」と呼ばれる。十七世紀以降の日本における経典類は、大半が、この近世訓点に属する林羅山の「道春点」で訓読されたのである。
そしてこの訓読の転換は、「単なる技法の転換ではなく」(同)、「朱子学受容と連動した、一種の思想的転回であった。」(同)桂庵点、さらには近世訓点一般の特徴は、「而」「矣」などの「助字」を丁寧に読んでいく点に求められるが、「この桂庵の、「置き字」一字一字を必ず訓読し、原文の一字一字をすべて日本語に直していこうとする姿勢は、経書の一字一字をすべて論理的、抽象的に概念規定し、解釈しっくしていく朱熹の注釈の方法に相応するものであった」(p.37)と中村は結論づける。「理一分殊」を理論的前提としつつ、格物致知の実践として入念に経書を注釈してゆく朱熹の姿勢の日本における対応物が、誰にでも公開された簡明平易な近世訓点なのである。
その後も、朱子学の「理」の思想を否定した荻生徂徳が、まさに訓読の廃止を提唱したり、さらには近世末期の知識人たちの骨身に染みついていた訓読文体が開化期の書記文体の母体となり、今日の日本の書き言葉までもその決定的な影響下にあったりと、「訓読」と朱子学とをめぐる問題圏は、さながら日本儒教史•日本語史•日本文学史•日本文化史等々の最肝要の結節点をなしているといって過言ではない。今日の日本人が読み、書く言語そのものが、朱子学のはるかな残響のもとにあるのである。こうした「訓読」の重要さについては、哲学・歴史学の方面の研究者のみでなく、もちろん文学研究者も注目するところであり[9]、現在「訓読」研究界隈は、おのずと活気ある学際研究の様相を呈してレ、る。V、っそうの成果が俟たれるところである。
知识出处
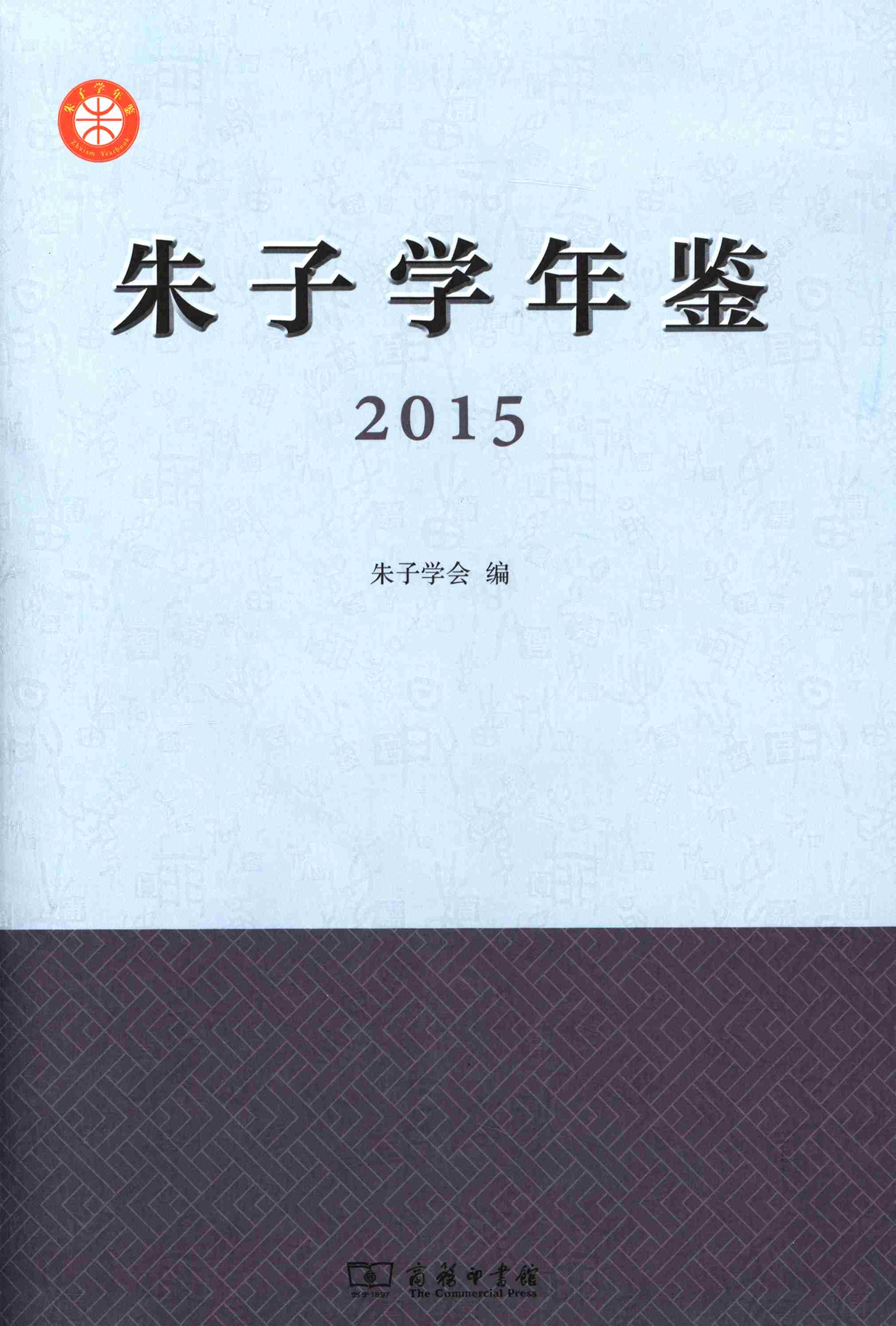
《朱子学年鉴.2015》
出版者:商务印书馆
本书主要内容有“特稿”栏目选登了清华大学国学研究院陈来教授和韩国成均馆大学崔英辰教授的文章,前者以李退溪与李栗谷的理发气发说为中心来探讨韩国朱子学,后者分析了韩国朱子学的心说论争研究现况。“朱子学研究新视野”栏目推介了杨祖汉教授的《论朱子所说的“诚意”与“致知”关系的问题》、杨立华教授的《朱子理气动静思想再探讨》、方旭东教授的《无思有觉、圣凡体别——朝鲜儒者李珥的“未发”说》、朱人求教授的《朱子“全体大用”观及其发展演变》、许家星教授的《朱子学的羽翼、辨正与“内转”——以勉斋<论语>学为中心》、方笑一副教授的《<近思录专辑>简介》、吾妻重二教授的《周惇颐墓——其历史与现状》等。“全球朱子学研究述评”栏目比较详细地梳理了2015年中国、美国、韩国、日本等朱子学的研究现状,介绍了目前全球朱子学研究的最新进展。“朱子学书评”栏目选刊了对《朱熹大辞典》《朱熹文学思想研究》《宋明理学十五讲》等著作的书评。“朱子学研究论著”“朱子学研究硕博士论文荟萃”“学者简介”“朱子学研究机构”“朱子学研究重大课题”“朱子学学术动态”“资料辑要”等栏目尽可能全面地展示2015年全球朱子学界的最新成果和学术动态。
阅读